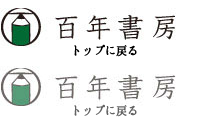いま、これだけパソコンやネットが普及した中で、あえて紙に印刷する理由とは何だろう? データとして残してしまえば、保管だって場所を取らないですむし、検索だって簡単だ。文字の大きさだって自由自在である。一昔前までなら想像もつかない便利な時代にあえて「書籍として残す」とは、どういうことなのだろう? かつて同じ出版社、同じ編集部に籍を置き、机を並べたアラフォーライター2人の対談。

大学卒業後、白夜書房入社。退社後、フリーのライター兼編集業を経て、2010年、株式会社百年書房設立。著書に『ホームレス名言集』(KKベストセラーズ刊)。「市井の人の本を集めた『百年書房文庫』のような場所をつくるのが目標」。

大学卒業後、白夜書房入社。退社後、フリーのライター兼編集業。主な著書に『パンラボ』(白夜書房刊)。パン好きに人気のブログ「パンラボ」主催。2014年4月には雑誌Hanakoで「パンラボ大特集」が組まれた。
- 藤田
- 池田さんはこれまで8冊の単行本を出版されているわけですが、著書『パンラボ』が好調です。
- 池田
- おかげさまで増刷が決定しました。
- 藤田
- 解説すると「パンラボ」というのは、パンに対してアカデミックにアプローチした、文化的ガイドブックです。ラジオやテレビ、新聞でも大きく紹介されています。ですが、ご活躍のわりには…。
- 池田
- 儲かっていません(苦笑)。ネットの世の中に反時代的な、儲からない仕事を選んでしまったものだと、後悔することもあるのですが、それでも愛着を持っています。
- 藤田
- 『パンラボ』の読者も、『パンラボ』に愛着を持っている感じがすごくします。
- 池田
- 書名と同タイトルのブログを開設しているのですが、トークショーなどをやるときに、読者がそのブログページをプリントアウトして持参してきてくれるんですよ。
- 藤田
- ウェブ上で見るだけでなく、わざわざプリントしてくれるわけですね。
- 池田
- そうです。熱心な読者の方はブログのページをプリントして、さらにそれをファイルなんかしてくれるわけですよ。それを何度も読み返してくれたりもする。
- 藤田
- パソコンだと目がチカチカするし、通読性においてはまだまだ紙に追いついていませんからね。いまの話にどこかヒントが潜んでいそうですが、パソコンやネットがこれだけ発達、普及している中で、紙の本の存在意義とは何でしょうか?
- 池田
- 僕たちの職業は本を作ることです。僕はね、自分の仕事を氷屋だと思っているんですよ。
- 藤田
- それはどういうことでしょう?
- 池田
- テレビで、都会の中に埋もれるように、昔ながらの仕事をつづけている氷屋の映像を見たのですが、それはとてもうつくしいものでした。コンクリートの三和土の上を、やっとこみたいなもので透明な氷のブロックをつかんで、滑らせる。
- 藤田
- 氷屋さん、まだあるんですね。
- 池田
- ありますよ。氷なんて、スーパーで買ったほうがよっぽど安く、便利なのかもしれません。でも、氷屋さんはたとえ儲からなくても、うつくしい職業に殉じているんだと思います。
- 藤田
- なるほど、氷屋的ね。少し寂しい気もするたとえですが…。
- 池田
- あるいはモノクロの映画ですね。先日、映画館で『大人はわかってくれない』というヌーヴェルヴァーグの傑作映画を見たのですが、はじまった途端、そのうつくしさに涙が出ました。いま、モノクロの映画用フィルムというのは製造されていません。もう地球上からは永久に失われてしまったうつくしさなのです。
- 藤田
- 絶滅の危機…。特に経済誌などでは「書籍の時代は終わった」という論調もあります。
- 池田
- たしかに経済的にいえばそのとおりかもしれませんが、ものというのは、終わった瞬間からうつくしくなると思うのです。それは氷屋しかり、モノクロ映画しかりですね。
- 藤田
- おおいに抗いたいし寂しいけれども、同意する部分もあります。本はいま、そういう瞬間を迎えつつあるのかもしれない。
- 池田
- ええ。いま選書家という職業が脚光を浴びています。松浦弥太郎さんや、江口宏志さんがそうですね。単に内容を評価する文芸評論家という職業とはちがいます。
- 藤田
- 装丁や造本といったうつくしさを評価していますね。大きくなりすぎて身動きが取りづらくなった大型書店に対抗する、セレクトブックショップがそういう選書家の人たちの仕事場になっています。
- 池田
- 内容ももちろんですが、カフェやギャラリーなどでインテリアとしての書籍が求められているのですね。こうした役目を書籍が担うようになったのは、むしろインターネットが普及して、本に頼らなくても情報が得られるようになって以降です。だから、やや飛躍した言い方をすれば、書籍の時代はいまはじまったのだといえるでしょう。
- 藤田
- なるほど。どうしても必要ではなくなった瞬間にこそ、真価が問われるのかもしれません。愛というか愛情というか、そういう感じ。
- 池田
- そうです。藤田さんの作ろうとしている「私家本」にしても、装丁とか紙質だとか、とても良い雰囲気じゃないですか。かっこいいし、愛情を感じるんです。
- 藤田
- ありがとうございます。
- 池田
- これ、新書だからこそだと思うんです。自費出版の場合、コスト的に作り込みという作業がどうしても限られてきてしまいます。私家本のプロトタイプを作るために、藤田さんがとても時間をかけて試行錯誤しているのを間近に見ているので余計にそう思います。
- 藤田
- 汎用性を意識しつつオンリーワンの本でなくてはいけない。そうして作られた本が親族や友人の間で宝物というか家宝というか、そういうものになるといいな、と。百年後に残っている本になってほしい、そんな願いをこめて「百年書房」と名づけました。
- 池田
- これ、新しいと思うんです。
- 藤田
- 古いけれども新しい、そう思っています。
- 池田
- ただ本にするとか、ただまとめる、ではなくて、うつくしい本になっているところがいいですね。
- 藤田
- 極端な話、これから紙の書籍は古典と、意外にも私家本だけになっていくのではないかと思うのです。10年経ったら古ぼけてしまうような本は、もう紙の書籍である必要がなくなってきている。
- 池田
- 10年どころか、1年で状況が激変している場合だってありますからね。これは自分が本を作るときにも、いつも意識していることです。何年か後に、この本はどう読まれるのだろうか、という視点ですね。
- 藤田
- 「ドッグイヤー」という言葉があります。嫌いなんですけれども、ITの分野だけではなくて、すべてがそんな目まぐるしい時代になってきています。そもそも本はそれとは真逆で、もっとスローなものではないかと思うわけです。
- 池田
- スローですよね。いまや書店にある本の寿命は本当に短くなってしまった。
- 藤田
- この場合、寿命というのは書店に並んでいる期間という意味で、これは本当に短いし、すぐに忘れられてしまう。
- 池田
- しかもそのサイクル短縮も加速しています。本というのはもともと、そんな消耗品ではなかったはずです。
- 藤田
- 本当にそう思います。その観点からすると、電子書籍の普及で紙の書籍が淘汰されるのは、決して悪いことばかりではないかもしれない。
- 池田
- 古典、または将来古典になりうるかどうか、選別された上で紙の書籍になるわけですからね。紙の書籍は激減する。でも、それは同時に本来の意味を取り戻すことでもある。
- 藤田
- よく言われるのが内容として区別される「ストック」と「フロー」。
- 池田
- 「ストック」というのは文字通り残していくもので「フロー」というのは流れている情報、ですね。
- 藤田
- 「ストック」として価値のあるものだけが紙の書籍で残っていく。
- 池田
- たしかに「私家本」はストックになる。
- 藤田
- 口幅ったい言い方になりますが、それは数万部観光されているベストセラーよりも価値があるのではないかと思うのです。
- 池田
- 近しい人にとっては、そうなります。
- 藤田
- そういう価値のある本を、これまでよりもずっとずっと身近に作ることができるようになりましたよ、というのが百年書房からの提案です。本日はお忙しいところ、ありがとうございました。